【第3回】筋トレのやり方で分かれる「機能 vs 見た目」
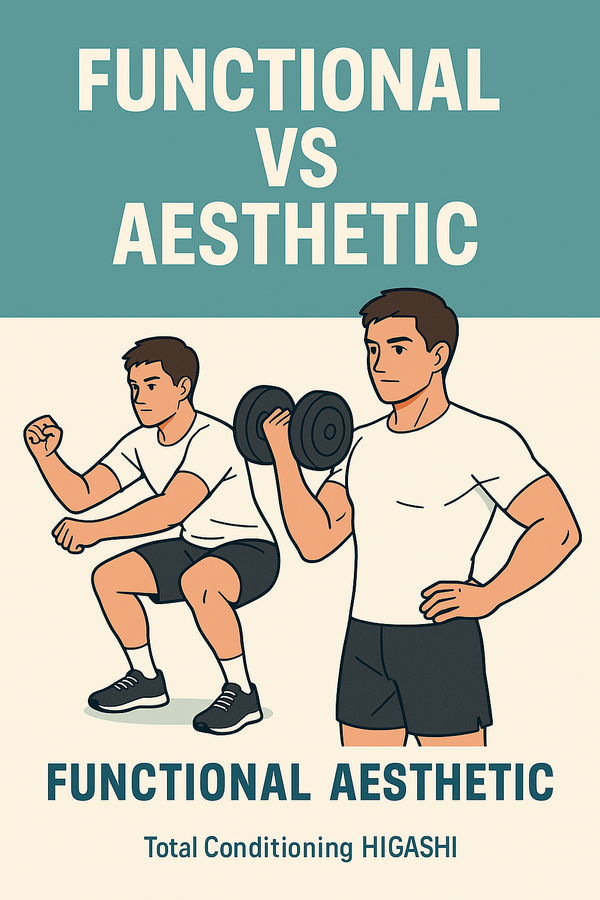
筋トレの目的が「動ける筋肉(機能的筋力)」なのか「見せる筋肉(審美的筋肥大)」なのかで、トレーニングの中身は大きく異なります。同じ“筋トレ”という言葉でも、体への影響や仕上がる体の質はまったく違うのです。
**“見せる筋肉”**を作るためのトレーニングは、高重量×低回数のウエイトトレーニングが主流です。ピンポイントで大きな刺激を与えるために、マシンやアイソレーション種目(例:アームカール、レッグエクステンション)を多用します。目的は筋肉を肥大させ、ラインをくっきり出すこと。全身の連動や動作の流れよりも、「特定の筋肉だけを太くする」ことに特化しているため、機能性より見た目重視になります。
一方、**“動ける筋肉”**を作るには、多関節運動や自重・バランストレーニングが基本です。スクワット・ランジ・プッシュアップ・ヒンジなどの動作を軸に、全身を一体として使う感覚を育てることが重要。ウエイトを扱う場合でも、バーベルスクワットやジャンプトレーニングなど、スピード・バランス・姿勢制御を伴う種目が中心になります。
このように、「どんな筋肉をつけたいか」によって、トレーニングの種目・負荷設定・動作の質がすべて変わってきます。アスリートにとって必要なのは、パフォーマンスを支える“動ける筋肉”。そのためには、「どんな目的で、どんな動きを作るのか」を意識してトレーニングを組むことが不可欠です。
Your body can move
身体を変える・未来が変わる
トータルコンディショニングHIGASHI
2021年10月24日 00:00


