【第3回】ケガのリスクを数値で把握
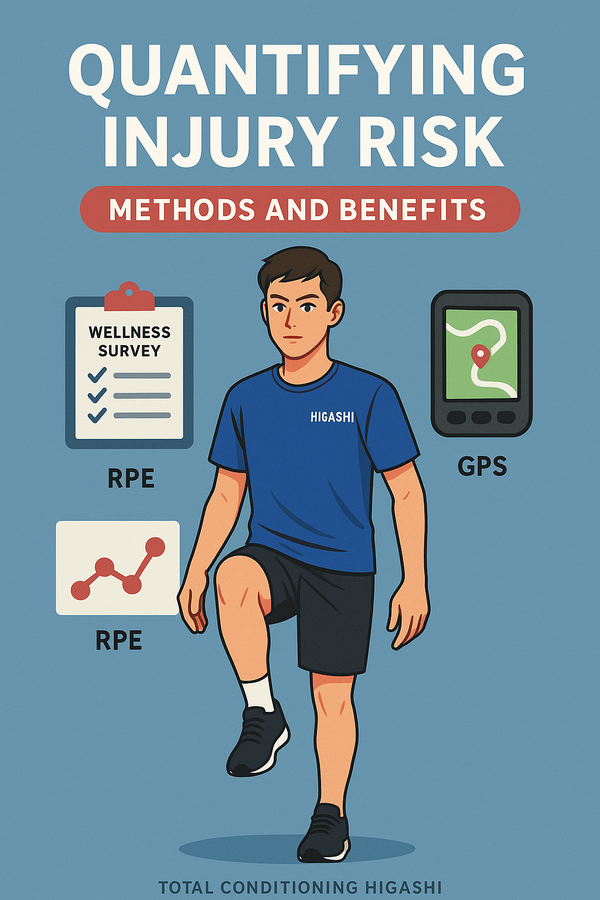
可視化する方法とメリット
選手の体調やケガの兆候は、「感覚」や「勘」だけで判断すべきではありません。現在、多くのスポーツ現場ではケガのリスクを“数値化”し、客観的な判断材料とする取り組みが進んでいます。これはトレーナーだけでなく、指導者や選手本人にとっても有効な「見える化」のツールです。
最も基本的なのは「体調アンケート」や「主観的疲労度(RPE)」の記録です。毎日の練習前に「疲労感」「痛みの有無」「睡眠時間」などを自己申告させることで、小さな変化を見逃さずに把握できます。簡易的ながら、継続すれば非常に価値のあるデータになります。
次に有効なのが、身体機能テストのスコア管理です。例として、片脚ジャンプ距離、バランステスト(Yバランステスト)、柔軟性チェック(シット&リーチなど)は、筋力や可動域の左右差・偏りを客観的に評価できます。明らかに数値に差が出た場合は、フォームの崩れや一部筋の過緊張が疑われ、ケガのリスクサインとして活用できます。
最近ではGPSや加速度センサーを使った「客観的運動量の管理」も注目されています。スプリント数・加速回数・減速の質などを記録することで、選手の負荷変化を詳細に追跡でき、過剰な負荷の予測にもつながります。
重要なのは、こうした数値を「記録して終わり」にせず、「指導と結びつける」こと。明らかに片脚の筋力低下が見られる選手には、片脚補強や動作改善トレーニングを加えるなど、具体的な対応が取れて初めて意味を持ちます。
数値は選手の「状態を見える化する武器」。感覚ではなく“科学的根拠”をもとにケガを予防する文化を、チーム全体で築いていきましょう。
Your body can move
身体を変える・未来が変わる
トータルコンディショニングHIGASHI


